キャンディ・キャンディ韓国正規版DVDは「正規版」ではありません
現在「キャンディ・キャンディ 正規版DVD」を称してネット通販されている韓国や台湾製のDVDソフトは、原著作者・水木杏子と東映アニメーションの許諾を受けずに製造販売されている海賊版です。
2007年の春から、韓国で許可なく<キャンディ・キャンディ>の不正アニメ放送が堂々と開始されてしまいました。
東映動画が講談社を介して取得していた『キャンディ・キャンディ』の放送権・ソフト化権は1995年に失効。未だ権利を保持していた時点で外国企業に許諾した放映権等も2001年までには全て失効しています。海外では期限切れの契約書を悪用した「正規許諾品のように偽装した海賊版」がしばしば販売されていますので、うっかり購入したり、正規品であるような誤情報を広めたりせぬようにくれぐれも気をつけてください。
尚、東映も原作者も許諾していない台湾海賊版を正規品と称して販売している齊威國際多媒體股有限公司(Power International Multimedia Inc.)は、台湾における いがらしゆみこ氏のビジネスパートナーです。
参照: 正規品を称する海賊版アニメDVDのカラクリ 原作者・水木杏子がアニメ『キャンディ・キャンディ』再放送に反対した事は一度もありません
原著作者・水木杏子(名木田恵子)は、東映アニメ『キャンディ・キャンディ』の再放送やソフト販売に反対したことはありません。それどころか裁判当時も判決後も「再放送はいつでもOK」と公言しています。
そもそもアニメ版キャンディ・キャンディを世に出せなくなったのは、原著作者と作画者の両名が(株)講談社との二次使用の契約を解除した為、(株)東映が作品を動かせなくなったからです。 キャンディ・キャンディの権利関係の基本
『なかよし』掲載最終回とアニメの放映日
ちなみに『キャンディ・キャンディ』の最終話が掲載された『なかよし』1979年3月号は2月3日発売。アニメ版最終話放映は、同年2月2日。
アニメの製作スケジュールからして、明らかに、最終話の脚本はいがらし作画の漫画原稿に基づくものではありません。 最終四話くらいは、原作者の先行提出したプロットから直接脚本執筆されているものと思われます(『巨人の星』も同パターン)。 にもかかわらす作画者は「最終話は原作を無視して自分ひとりで描いた」と吹聴してまわっているのです。 キャンディ・キャンディ事件の発端
『キャンディ・キャンディ』の大ヒットにより若くして原稿料の高い大御所作家になったものの、その後のオリジナル作品では顕著な売り上げを出せずに90年代半ばからは講談社からも干されるようになった作画者・いがらしゆみこ。
同じ頃、いがらしゆみこの同郷の友人である本橋浩一が代表取締役社長をつとめていた日本アニメーション株式会社も、シリーズの視聴率低下により伝統ある名作劇場放映枠を失いつつありました。 そんな作画者・いがらしゆみこと日本アニメーションは、『キャンディ・キャンディ』を名作劇場枠で再アニメ化して、フジサンケイグループぐるみのキャラクタービジネスをもくろんだのです。 いがらしゆみこは「講談社はキャンディは要るけどいがらしは要らないのよ」と不遇を訴えて、原著作者・水木杏子に哀願。 迷った末に講談社との義理よりもいがらしとの友情をとった原著作者・水木杏子は、いがらしと共に講談社との契約を解除(1995年2月26日)。 講談社との契約によって放映権その他を持っていた東映としては、新たに水木・いがらし両氏と契約を結びなおさなければ『キャンディ・キャンディ』の放映・ソフト化はできません。 なので当然、東映の担当者は新たな契約に関する打ち合わせをするべく、両者にコンタクトを求めて何度も書面を送りました。原著作者・水木杏子も同様に、作画者・いがらしゆみこに何度も連絡をしました。 しかし作画者・いがらしゆみこは居留守をつかって話し合いを忌避。 その間に作画者・いがらしが何をしていたかといえば、原著作者・水木にも商標権保持者の(株)東映にも無断で管理を任せたフジサンケイアドワーク(現・クオラス)と共に『キャンディ・キャンディ』キャラクターグッズの許諾を多数の企業に行っていたのでした(1996年秋)。 バンプレストの災難
そのフジサンケイアドワークといがらしゆみこから許諾を受けた会社の一つが、(株)バンプレスト。
バンプレストの担当者・吉田明氏曰く (略)
吉田明氏は往年のキャンディブームの際、ポピーの関連会社の「吉田企画」でキャンディ人形を企画制作した経歴のある人。
水木杏子がポピーの「ポピーちゃん人形」のタイアップ漫画「うたえ!ポピーちゃん(作画:原ちえこ)」「あいLOVEポピーちゃん(作画:峡塚のん)」を『なかよし』誌上で連載していたこともあり、その縁がその後の『なかよし』とポピー、バンダイの長い蜜月のひとつのきっかけとなっている模様。 ちなみにその後、「バンプレストの担当者」は配置換えになったようです。 いがらしゆみこ公式サイトにあった文章によると、 水木さんの異常な抗議にバンプレストは承諾を得ることを断念しました。
…との事ですが、ダミー会社の実態の確認ミスで、バンプレの得意先である東映と権利トラブルの最中であるいがらしゆみこに加担してしまった事で、詰め腹を切らされたというのが実情でしょう。
当サイト内の関連記事: 『キャンディ・キャンディ』のプリクラ(プリント倶楽部/写真シール機)について 商標権問題
東映及び原著作者・水木杏子は、地裁判決後いがらし側が上告して更に争うことがなければ違法グッズを追認して事態を収拾するつもりでいました。
水木杏子公式サイト掲示板過去ログより 信用を失うということ ◆ 水木杏子 2002-04-16 (Tue) 23:32:43 アジアに広がった作画者発の違法キャンディ・キャンディグッズ
原作者・水木杏子の願いもむなしく、作画者・いがらしゆみこは裁判中も敗訴後も「水木とは和解した」「上告したから判決は確定していない」と業者に更なる違法キャンディビジネスを煽りました。
尚、高裁に上告する際にいがらし側弁護団が利用したのが、現在マンガ学会監事をつとめている牛木理一 弁理士の論文「連載漫画の原作とキャラクターの絵との関係(『パテント』1999年7月号)」。 東映はこの後数年間、国内外(香港、マカオ、中華人民共和国、シンガポール、マレーシア、ブルネイ、台湾、タイ、ハワイ)で販売された、自社の商標権を侵した多量の『キャンディ・キャンディ』グッズへの対応に悩まされることになります。 東映といがらしゆみこが完全に決裂した商標登録無効審判
更に作画者・いがらしゆみこは2001年7月10日に東映アニメーションに対して商標登録無効審判を起こしますが、これは却下されました。
1999年8月23日付けで、原著作者・水木杏子と東映との間で「『キャンディ・キャンディ』の名称を東映アニメーションが商標登録することに同意する」旨の同意書を締結していた為です。 水木杏子公式サイト掲示板過去ログより アニメと商標権について ◆ 水木杏子 1999-10-18 (Mon) 23:24:09
いがらしゆみこ公式サイト(旧)より
◆いがらしゆみこから水木さんへ Ⅱ 2000年12月27日 日本マンガ学会監事・牛木理一 弁理士の論文
この商標登録無効申し立ての際、いがらし側が「東映が商標を抑えているのは不当」という主張の根拠に利用したのが、これまた現マンガ学会監事・牛木理一 弁理士の論文。
1976年当時は、出版社はキャラクターマーチャンダイジングを直接行うノウハウは持っていませんでした。 出版社が意識的にアニメ化とグッズの版権管理をやりはじめたのは、1981年の『ドクタースランプ』あたりからです。 ですから、当時としてはアニメ会社の(株)東映に商標権を取得させ、管理を任せた方が作家・出版社ともに効率の良いビジネスが出来る、現実的な対応であったと言えます。 当時も、その後の二十数年間も、東映は何ら背信行為を犯すことなく誠実に『キャンディ・キャンディ』のブランドイメージを高め、保持してきました。 また、ローティーン向け少女漫画雑誌『なかよし』の人気作品であった漫画『キャンディ・キャンディ』を幅広い年齢層にアピールするタイトルに育て上げ、更に海外でまで知名度を高めたのは東映の功績です。 「不当」といわれる筋合いはありません。 再放送の為のハードル
このように東映の商標権を侵して多数の違法グッズを世界中にばら撒き、東映に対し商標登録無効審判を起こす一方で、作画者・いがらしゆみこは東映に対し、「再放送をいつでも許諾する」との申し入れもしています。
そして、原著作者・水木杏子も「再放送はいつでもOK」と表明しています。 原著作者は権利関係にうといまま作画者の口車に乗って講談社との契約を解除してしまった為に、ビジネス上の混乱をまねいたことを非常に反省しています。 また「アニメ版は自分だけの作品ではなく、フィルムを作った多くの東映スタッフや声優たちのものでもある」「海外では漫画版を知らないアニメのみのファンが多い」という認識なので、「東映の権利を侵した違法グッズさえ始末がつけばアニメの許諾は可能であろう」と常々公言していました。 商標権と海外のアニメのこと ◆ 水木杏子 1999-08-18 (Wed) 15:04:10 アニメーションのリメイクについて 名木田恵子 いがらしゆみこの「漫画原作者の権利否定」に追従した日本マンガ学会
しかし、作画者・いがらしゆみこは裁判が終わった後もさまざまな場で「水木杏子は原作者ではない」と公言しています。
良識派の漫画家や編集者はこのようないがらしゆみこの言動には眉をひそめていますが、長谷邦夫、牧野圭一のように「漫画原作者の権利否定」に追従する業界人も少数ながら存在しています。 この両名が参加している日本マンガ学会にいたっては、原著作者である水木杏子に出席のオファーすらせずに、作画者・いがらしゆみこのみに都合のいい主張をさせて最高裁判決を否定する事を目的としたフォーラムを開催。 参照外部リンク: 水木杏子公式サイト内「アニメの再放送について」 400字詰原稿用紙2,000枚の原作原稿=「走り書きの文字原稿」
いがらしゆみこの顧問弁護士と親しい日本マンガ学会監事・牛木理一 弁理士は、かねてより「アニメーション映画の製作者という二次的著作物の著作権者の立場にすぎない東映が商標権を専有しているのは問題あり」と主張していました。
それが更に「走り書きの文字原稿(=400字詰原稿用紙2,000枚分の小説形式の原作原稿を指す)」を書いただけの水木杏子を原著作者と「決め付けた」最高裁判決も不当と発言。 そして日本マンガ学会著作権部会は「いがらしゆみこが東映の商標権を侵して無断で制作したグッズ」に対して販売許可を出さずに差し止めた原著作者の行為は「正当な理由がない権利の濫用」であるから、グッズ業者は原著作者に対して裁判を起こすべき、という提言までする始末。 そして現在、国内で販売差し止めされた違法キャンディ・キャンディグッズが韓国で大量に販売されているという報告もあります。 東映アニメーションの立場
作画者が原著作者の権利を否定している現状では、東映としても新たな契約書など作れるものではありません。
70年代に製作された全115話のフィルムをデジタルリマスターにかけるには、相当の費用がかかります。 やっとリマスターを終了しソフトの生産を行っている途中で、また新たなトラブルが起こって発売中止になった場合、東映の損失は莫大なものになります。 そんなバクチは営利企業として打てるはずもありません。 以下、水木杏子公式サイト過去ログ発言。 アニメの再放送の誤解のことなど ◆ 水木杏子 2002-05-13 (Mon) 16:43:45 No.146 >おたずねのことなど
…という訳なので、原著作者・水木杏子と(株)東映アニメーションには、アニメ版『キャンディ・キャンディ』お蔵入りの責任はありませんので、その点ご理解ください。
文句を言いたいなら作画者・いがらしゆみことそのシンパの日本マンガ学会にね。 追記
作画者は2007年台湾で『キャンディ・キャンディ』のメインキャラに酷似した、『甜甜Lady Lady』と称する「オリジナル新作」のキャラクタービジネスを展開。
最高裁判決を愚弄するのみでなく、東映が保持している『レディレディ』の商標権を侵害する行為であり、東映アニメーションといがらしゆみこの関係修復は暗礁に乗り上げたと見てよいでしょう。 キャンディ・キャンディ事件解決の為に最大限の尽力をした講談社
梶原一騎の著作権を否定した いがらしゆみこ
まず地裁における いがらしゆみこ氏の主張を記します。
<証人尋問>でいがらし氏はこう証言しています。
つまり、原作者がキャラクターデザインにまで参加し、作画資料を提供し、ネーム形式で書かれた原作原稿でない限り、「漫画原作」としての法的権利は有しないという主張です。
漫画『キャンディ・キャンディ』の原作は400字詰原稿用紙2,000枚超に書かれた小説形式のものである為に、「原作」ではなく単なる「参考資料」に過ぎないというのです。 近年はネーム形式の原作者も増えましたが、日本の漫画史を築き上げてきた多くの漫画・劇画原作者、例えば梶原一騎、福本和也、小池一夫、雁屋哲、武論尊、牛次郎、工藤かずや、佐々木守… といった大御所作家たちの原稿は小説形式や脚本形式で書かれています。 万が一にも いがらし氏の主張が法廷で認められ、判例となっていたら、このような大御所作家たちの著作権は否定され、彼らが人生をかけて紡いできた物語は「単なる参考資料」に貶められ、創作者としての名誉も法的権利も奪われてしまうところでした。 そのような悪夢を防いだのが、講談社が裁判所に提出した仔細な陳述書だったのです。 講談社の『キャンディ・キャンディ』担当編集者(企画立ち上げから第3部完まで)だった清水満郎氏が98年3月、地裁に提出した陳述書の要約1.『キャンディ』の誕生理由
また、事件以前は いがらしゆみこ氏自身も「企画は編集部」「自分に話が持ち込まれた時には既に原作をつけることが決まっていた」と公言していました。
参照: アニメック第23号(昭和57年4月)ザ・プロフェッショナル第四回 「原作付き漫画」の著作権
講談社版権事業推進部長・新藤征夫氏が98年10月、地裁に提出した陳述書の要約。
1.「原作付き漫画」の著作権
新藤氏は地裁判決の翌朝の新聞にも同様のコメントを寄せております。
漫画「キャンディ・キャンディ」の版権を以前管理していた出版元の講談社の新藤征夫・版権事業推進部長の話 講談社顧問弁護士の見解
講談社社史編纂室部長・竹村好史氏 談
――――講談社が「原作が原著作物である」という判断をしたのはなぜですか?
(株)講談社の見解では初めから「水木杏子は”原著作者”」であり、連載時からその見解に沿った法的処理がなされていました。
にもかかわらず、日本マンガ学会では「最高裁判決で水木を原著作者と位置づけたのは、漫画界の実情を反映しない不条理な判決」とネガティブキャンペーンをはり、原著作者をカヤの外に置いて作画者一人を著作権フォーラムにまねき、最高裁判決を非難しました。 そればかりでは終わらず、 日本マンガ学会著作権部会は、2005年10月13日の第3回著作権部会の席上で 「キャンディ・キャンディ」のマンガ部分は、二次的著作物という解釈ではなく、ストーリー部分との共同著作物であるとなぜ解釈できないのか。
等と最高裁判決及び講談社法務部の法的見解を非難し、原著作者・水木氏と商標権保持者である(株)東映アニメーションの正当な権利を侵して違法グッズを制作販売した業者を「被害者」と位置づけ、新たな裁判を起こすための扇動まで行っています。
「いがらしの為の企画」ではなかった
講談社社史編纂室部長・竹村好史氏 談
「『世界の名作のいいところを全部出せないか』というようなコンセプトだったと思います。そんな露骨な言い方はしなかったとは思いますが……。 東京地裁の判断
東京地裁判決文
しかし、本件においては、前記第二、一(前提となる事実関係)に証拠(甲一、一二、丙一の1ないし5、二の1ないし4、三ないし七、九、一〇)及び弁論の全趣旨を総合すれば、 講談社側の証言まとめ
講談社側の証言を総合すると、
ということのようです。 日本マンガ学会理事が教育現場を含む様々な場で吹聴している、「少女マンガの女王いがらしサンに、新人だった水木さんは当初言われるままに書かされてきた」が真っ赤な嘘であることは明白です。 講談社が再びキャンディ・キャンディの著作権管理をする可能性
講談社社史編纂室部長・竹村好史氏 談
――――講談社が再び著作権を管理するという話はなかったのですか?
いがらし側の意向は不明ですが、原著作者・水木杏子氏の方は作画者の口車に乗って講談社との契約を切ったことが一連の横領詐欺の始まりであり、
この事件後、すべてを元に戻し講談社、東映アニメに私の権利を任せることができたらと願っております。
と表明しています。
また、漫画本に関しては 水木は講談社以外、許可しないつもりですが、その版元、講談社でさえ問題がきれいに解決しない限り、出版することはないでしょう。
とも宣言しています。
現在、講談社と『キャンディ・キャンディ』という作品の間には、何の法的関係もありません。 講談社がふたたび『キャンディ・キャンディ』を出版・版権管理をするには、新たに水木・いがらし両氏と契約を結び直さねばなりません。 その際には当然、講談社法務部の以前からの法的見解であり、最高裁判決によっても再度確認された「水木杏子は原著作者」「漫画作品『キャンディ・キャンディ』は原作原稿の二次的著作物」に則った契約書が作成されるはずです。 しかし、作画者・いがらしゆみこは現在も「最高裁判決は不条理」「水木を原著作者とした最高裁判決は不当」「原作と称する文字を書いただけの人に絵に関する権利を与えるなど受け入れられない」と、公私にわたって主張しており、日本マンガ学会も作画者の主張に同調しています。 このような現状では、講談社としても復刊のためのアクションはとれません。東映アニメーションの立場も同様です。 また、現在にいたるまで、作画者・いがらしゆみこは、原著作者・水木杏子氏、商標権保持者・東映アニメーションに対し、何の謝罪も表明しておらず、今まで行ってきた不正ビジネスに関する情報公開も拒んでいます。 事件が未解決のままでは、作品の正常化は到底不可能です。 その様な現状に加え、日本マンガ学会が原著作者・講談社・東映を陥れるような情報操作を行っている上、違法グッズ業者を煽って新たな裁判を起こす「提言」までしているのです。 事件の沈静化とキャンディビジネスの早期正常化は、原作者・講談社・東映、そしてファンの切なる願いでした。 しかし、その願いは日本マンガ学会の介入によって踏みにじられました。 日本マンガ学会理事等によって流されたデマ(「講談社は裁判で証言しなかった」等)が正され、紛糾した事態が治まるまでには、長い時間が必要でしょう。 (略) |
カテゴリ
すべて
アーカイブ
2月 2022
|

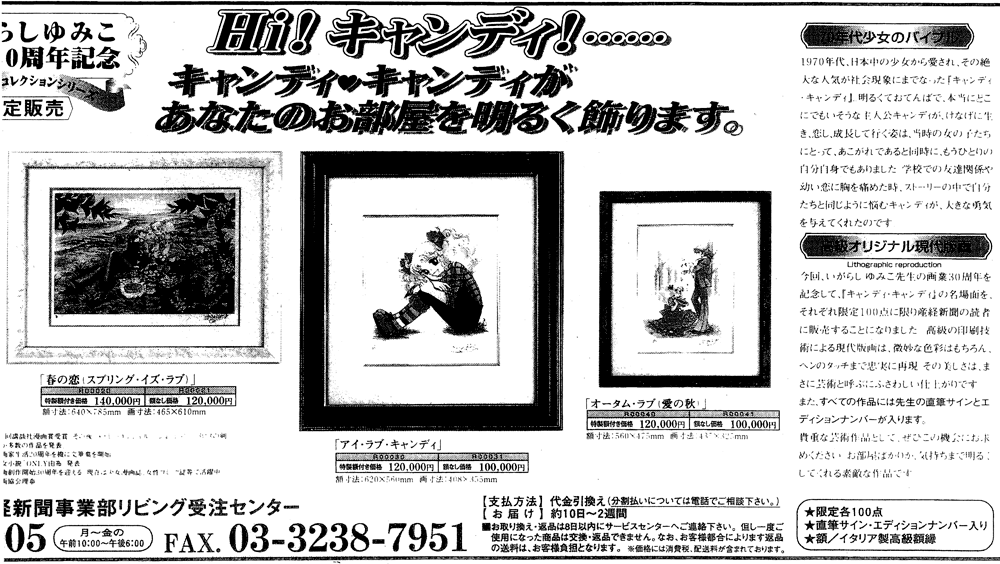



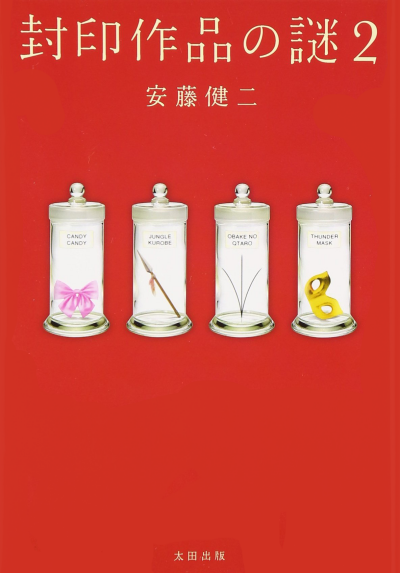
 RSSフィード
RSSフィード
